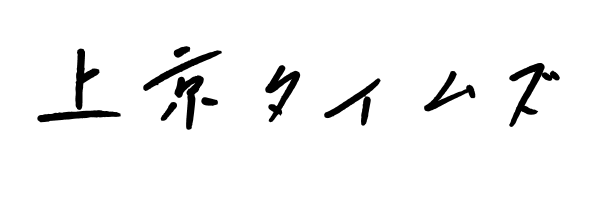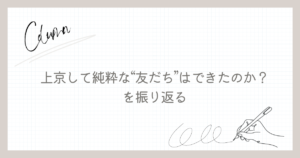身の程を知らされた街、東京
上京したい人のために、リアルな上京体験談を発信する上京情報メディア『上京タイムズ』。&Tokyoのコーナーでは「私と東京」をテーマに、読者から寄せられた東京にまつわるエピソードをお届けします。今回の記事を執筆してくれたのは、種山 颯太さんです。
“デビュー”を果たした専門学生時代

人には誰しも「調子に乗っていた時代」が一度はあると思う。振り返るだけで赤面してしまうような、くすぐったくなるような、そんな時代。私にとってのそれは、今から約二年前の専門学生の頃である。
神奈川県の田舎で小中高と育ってきた私だが、高校卒業後は蒲田にある専門学校に進学した。当時私はアイドルの応援、いわゆる「推し活」に熱中しており、何かしらでアイドルに携わる仕事をしたいという漠然とした目標と安易な発想で、専門学校への進学を決めたのだ。
夢を追いかけて東京の専門学校へ、などと言えば聞こえはいいのだろうが、実際はそこまでの気概と情熱があったわけではない。大学に進学する学力もなければ、高卒で社会の荒波に揉まれる度胸もなく、モラトリアムの確保的な理由も大いにあったし、大都会東京への漠然とした憧憬から進学先を決めたという側面もある。
そんな生半可な動機だったということもあり、専門学校での二年間はまさに「人生の夏休み」を体現するような為体であった。
高校時代の私は地味でクラスでも目立たず、煌びやかな高校生活を送っている同年代の者に対して僻み根性を炸裂させていた。そのような私が専門学校に入学した途端、髪をブリーチし、友人と大声で話しながら我が物顔で校内を闊歩し、居酒屋に入り浸って飲めない酒を無理やり飲んだり、咳き込みながらも紫煙をくゆらせたりしていた。
いわゆる「デビュー」を果たしたのだ。
周囲からは冷笑されることもあったし、今振り返ってみてもかなり痛々しい学生だったと思うが、とにかく充実した二年間だった。社会の厳しさなんて、人の視線なんて、客観視なんてどこ吹く風。どこにでも行ける、なんにでもなれる、なんでもできるという全能感で満ち溢れていた。
そんな二年間を東京で過ごしたということもあり、私は東京という場所にものすごく居心地の良さを感じていた。煌びやかで、なんでもあって、楽しくて、自分を開放できる場所。東京へのそんな印象は、きっと社会人になってからも変わらないだろうと思っていた。
しかし、社会人になってから、私は充実した専門学生時代とは正反対の生活を歩むことになる。
社会を知って失われた全能感

私は、東京にある会社に就職した。しかし、本当に恥ずかしい話だが、新卒で入社した会社は一ヶ月、次は半年、その次も半年で退職してしまったのだ。正当な理由は何もない。ただ単に、私に堪え性と社交性がなかっただけの話である。
どの会社でも生得の鈍臭さと不器用さと怠惰を露呈してしまい、その度に叱られ、周囲の人間を呆れさせてきた。そうなると根が無能なくせに人一倍プライドが高い私は、プライドを傷つけられた瞬間にすぐさま会社を辞めるという選択肢を取ってしまったのであった。
そして幼少期からの廃疾でもある“青い鳥症候群”を炸裂させ、「この会社が悪いだけだ」「俺にはもっと輝ける場所があるはずだ」と自分に言い聞かせて、転職を繰り返したのである。専門学校の二年間で得た全能感と自信と勢いは完全になくなり、私のプライドは完全にへし折られた。
私は、身の程を知った。
自分は大した人間ではないこと、秀でた才能など何もないこと、何者にもなれないということを知った。あれだけ楽しい思い出しかなかった東京の地で、私はこの二年間泥水を啜り続けた。「お前はだめだ」と東京に言われているような気がした。
あの頃抱いていた「どこにでも行ける」という感覚は、ただのまやかしであることを知った。
崩折れた先で

三度の短期離職を繰り返しているうちに、私は早くも社会人三年目を迎えていた。
同い年の大卒組も社会へと羽ばたき、それぞれが悪戦苦闘しながらも社会人生活を着実に送っている中、私は未だにちゃらんぽらんで、少し前に始めたアルバイトさえ二週間で辞めてしまっていた。
流石に今回ばかりは親にも話せず、いわゆる「エア出勤」を敢行していた。朝いつも通りの時間に家を出て、適当に夜まで時間を潰し、何食わぬ顔で帰宅する。22歳にもなってこんなことをしているのはどうにも飽き足りないが、こうするより他はない状況だった。
エア出勤を二週間ほど続け、行く場所もいよいよなくなってきたある日、私は時間潰しのために母校である蒲田の専門学校に行くことを決めた。無論、校舎には入れないだろうが、敷地内にはだだっ広い中庭があり、そこにあるベンチに座ってひとまず時間を潰そうと思ったのだ。
朝の九時ごろに到着し、誰も座っていないベンチにどかっと腰を下ろす。すると、丁度通学ラッシュの時間帯ということもあり、専門学生が次々とベンチに座る私の目の前を横切った。

信号機のように色とりどりな髪色の三人組、手を繋ぎながら歩く学生カップル、ギターケースを背負った個性的な出で立ちの男の子。見た目こそバラバラなものの、彼ら彼女らは共通して「キラキラ」していた。自分自身の可能性を信じて疑わない人間特有のオーラを放っていた。
直視できないほどに眩しかった。
きっとこれから沢山のことを全力で学び、全力で遊び、時にさぼったり道草を食ったりしながら前に進んでいくんだろう。自分たちが思い描く未来に向かって、全力で突き進んでいくのだろう。
まだこの学校を卒業してから数年しか経っていないというのに、なんだかひどく年老いた気持ちでその学生たちを眺めていた。そして、しばらくそうしているうちに気づいた。
数年前まで、自分もこうではなかったかと。目の前の彼らが持つエネルギーと全能感を、自分だってついこの間まで持っていたではないかと。

そのはずなのに、社会に出て沢山失敗をして、傷ついて、傷つけて、期待するのを辞めて、殻に閉じこもって、自分には何もできないと勝手に決めつけているだけではないか、と。
そう考えた途端、目の前の学生たちにあの頃の自分が重なり、目頭が熱くなった。もう一度あの頃の気持ちに戻ってもいいのではないかと思えた。
身の程なんて知ったって、自分ができないことを数えたって、謙虚さを身につけたって、いいことなど一つもなかった。周囲に馬鹿にされながらも身の程を知らず、知ろうともせず、調子に乗っていたあの頃の方がよっぽど楽しかった。
いつまでも楽しかった過去に思いを馳せるなんてダサいと言われるだろうが、私は過去を振り返るのは悪いことだと全く思わない。いつだって自分の背中を押してくれるのは過去だからだ。いつだって追い風は過去から吹き始めるからだ。
東京は、私に可能性と自信を与えてくれた場所。
東京は、私に身の程と不甲斐なさを知らしめた場所。
東京は、私に身の程を捨てるという選択肢を、再び与えてくれた場所。
ベンチから立ち上がって空を見上げる。今日は雲ひとつない快晴だ。
この東京の青空の下で、今日も誰かがもがいている。
文:種山 颯太